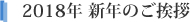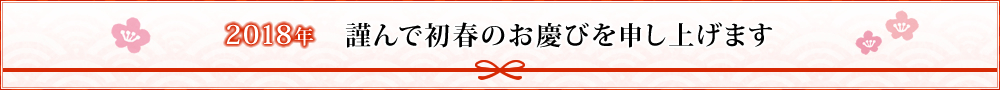
新年あけましておめでとうございます。皆さまにおかれましてはお健やかに初春をお迎えのことと存じます。
平成の御代も30年目を迎えましたが、来年は改元が決定しているという点でいつものお正月とは違う気分です。まるまる1年間が平成であるのは今年が最後となります。
元号が我が国に制定されたのは大化の改新以降で、以来1373年に渡って (南北朝時代には元号が2種類あったこともありましたが…) 連綿と続いて参りました。1868年に明治となった以降は一世一元の詔が発せられ在位中での改元が行われることはなくなりました。その原則は変わらないのですが、ご譲位による改元が行われるのは明治以降初めてです。
私が中学生になる頃に“明治は遠くなりにけり”の言葉が新聞やテレビで使われていたことを覚えています。その頃が明治百年にあたっていたので感慨を込めて使われていたと思いますが、当時は子供でしたから言葉通り受け止めたのみで、そうなのかぁ…以外の感想はありませんでした。この言葉が、俳人中村草田男氏が昭和初期に詠んだ“降る雪や明治は遠くなりにけり”に由来することは高校生になって知りました。
平成の次の新しい元号を迎えるとなると、まさに“昭和は遠くなりにけり”です。内科医になりたての頃の患者さまの多くは明治か大正のお生まれ。昭和はいらしても戦前の方で戦後生まれの方は珍しい存在でした。当然と言えば当然ですが、今は昭和生まれ、しかも戦後世代の方がほとんどを占めています。
元号は暦の表記法ですが、西暦表記は連続するものであるのに対して元号は非連続と言うか有限のもので、ある時点でリセットされ振出しに戻る点に大きな違いがあります。元号表記で不便な点は何といっても年齢計算…昭和なら25を足せば西暦、平成なら88を足せば西暦になるのはわかっていますが少々面倒くさい。一方、昭和生まれ…と言えば何となく気質がわかると言った便利な点もあります。もちろん昭和世代と言っても戦前と戦後では教育環境が全く異なりますし、戦後世代も高度成長期と安定成長期では(境目は昭和49年頃か?)平均的な生活水準が異なりますので一括りにすることには無理がありますが……
いずれにしてもやがて昭和世代…特に安定成長期以前に生を受けた者は何らかの揶揄の対象になっていくのかなぁ…と少々危惧しています。例えば「昭和30年代のお生まれですか…若く見えますねぇ…」とか「あの人はすぐにあんなことを言うけど昭和30年代の生まれなんだから理解してあげなよ…」とかなんとか。もっとも揶揄の対象になるのは少数派になるからで、還暦以降の日本人が多数を占めている現在は大丈夫…なんてことをおっしゃる方もおられます。
さて、皆さまにとって平成とは? ちなみに私は昭和の名のもとに32年間、平成の名のもとに30年間過ごして参りました。大学院を修了したのが昭和62年だったので、さしずめ私にとっての昭和は学習の時期、平成は医師としての力を蓄える研鑽の時期であったと言うことになりましょうか。
平成になってから天安門事件→ベルリンの壁崩壊→湾岸戦争→ソビエト連邦崩壊→バブル経済崩壊→阪神・淡路大震災→地下鉄サリン事件→アメリカ同時多発テロ→イラク戦争・アフガニスタン紛争→インターネット普及→リーマンショック→自民党下野→東日本大震災→再度の政権交代など様々な節目がありました。その時に自分がどんな状況にあったのかすぐには思い出せないことの方が多いのですが、阪神・淡路大震災と東日本大震災だけは別です。特に平成23年3月11日の東日本大震災発生時は金曜日午後外来の真最中であまりの横揺れの時間の長さに肝を冷やすとともに、被害の甚大さが判明するにつれて思考停止に陥ったものでした。直接被災しなかった者が言葉にするのは烏滸がましいとは存じますが、あの大災害前と後では安全・安心に対する考え方が大きく変わりました。震災によって引き起こされた原発事故の時には“想定外は許されない”との言葉も耳にしましたが、私は逆に想定外のことは必ず起きるものだ…との教訓を得たと思っています。
さて、想定外のことは必ず起きるとしても我が国が崩壊するようなことは絶対に起きて欲しくはない。不穏当な発言ですが、歴史の必定の中で再び戦争が起きることは避けられないかもしれない。でも内部崩壊だけはして欲しくない。その点で今危惧するのは格差の問題です。「ローマの滅びたるは中堅なくして貧富の縣隔甚だしかりしが故なり。秋山好古」秋山好古氏は司馬遼太郎氏の「坂の上の雲」に登場する主人公秋山真之氏の兄で陸軍大将まで出世された方です。2009年~2011年にかけてNHKでドラマ化された時には阿部寛さんが演じておられたのでご記憶にある方もおられるのでは……。好古氏は本邦の強みは格差が少なく中堅がしっかりしていることにある…、との信念をお持ちだったそうで、晩年は郷里松山の中学校校長を務められました(陸軍大将まで上り詰めた方としては異例のことだったとか…)。この警句は現在にも通じるところが多いと感じます。経済のグローバル化と産業構造の変化で所得格差が大となっている…、と喧伝されています。加えて高齢化の進行で若年層の負担が軽くなることは当分見込めません。霞が関には有能な方々が揃っておられると信じておりますが、私たちが安心して日々を送れるように医療・福祉の対策は平成の御代のあとも最優先の課題として取り組んでいただきたい…、と強く願っております。
来年の4月から5月にかけては10連休も想定されているとのこと。日本全体がこのような長期の連休を経験するのは、これまでの常識ではまさに「想定外」のことですが、どのような事態においても、当病院は患者様や地域の皆さまのためにスタッフ一同、力をあわせて円滑な病院運営を実践し続けて参りたい、との意を強くしているところです。
心臓血管センター 金沢循環器病院
病院長 池田 正寿